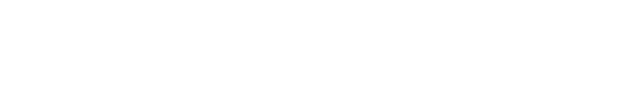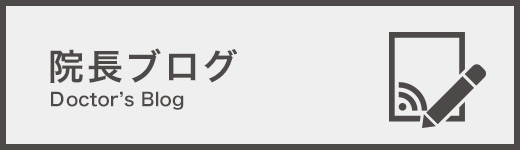弁膜症について
弁膜症とは
心臓と心臓の部屋の間、心臓と血管の間にはドアのように働く弁があります。
心臓には4つの弁があります。
図の左から三尖弁、肺動脈弁、大動脈弁、僧帽弁といいます。
ここでは左心室関連の僧帽弁(左心房と左心室の間)、大動脈弁(左心室と大動脈の間)の病気、弁膜症をご説明します。診断は心臓超音波検査で行います。
僧帽弁狭窄症・・・僧帽弁に解放制限がかかり、弁が完全に開かず狭くなっている状態です
最も多いのがリウマチ性(リウマチ熱由来、近年の日本での発症はまれで年間数例と言われています)で、幼少期に急性リウマチ熱を発症した時に僧帽弁が変性して、10年以上の無症状期を経て、狭窄症を発症すると言われています。進行すると肺高血圧・心不全を発症します。近年では高齢化や透析患者の増加により、石灰化や加齢性変化によるものもみられています。
手術やカテーテル治療適応になる目安は自覚症状の有無、重症(弁口面積1cm2未満)、平均圧格差15mmHg以上、心房細動の出現や血栓塞栓症の出現などです。保存的に経過を見る場合は、高血圧の管理や不整脈の管理、脈拍数管理になります。経過観察する場合は定期的に超音波検査を行っていきます。
僧帽弁閉鎖不全症・・・僧帽弁がうまく閉まらず、逆流が生じている状態です
器質性のものと機能性のものに大別されます。
器質性は僧帽弁逸脱症、腱索断裂、リウマチ性、加齢性等でひきおこされます。機能性のものは弁そのものには異常がありませんが、拡張型心筋症や心サルコイドーシス、虚血性心疾患により二次的に引き起こされるものを指します。
ガイドラインに沿って手術適応が決まってきますが、中~重症の閉鎖不全症に対して、検討していく形になります。器質性のものは重症度が高ければ手術が基本になりますが、どちらも内科的な管理(高血圧や心不全・不整脈に対する薬物治療)も並行して行い、経過観察する場合は定期的な超音波検査を行っていきます。
大動脈弁狭窄症・・・大動脈弁に解放制限がかかり、弁が完全に開かず狭くなっている状態です
大動脈弁狭窄症の主な原因として、加齢性が増えています。現在全体の80%を占めるともされています。ほかには先天性の二尖弁によるもの、リウマチ熱によるものがあります(リウマチ熱は日本では現象しています)。
大動脈弁狭窄症は症状が出る(狭心症症状・失神・心不全症状)と非常に予後不良の厳しい疾患です。症状出現からの進行が急速であり、早期発見が重要になります。
心不全症状では2年、失神では3年、狭心症症状では5年で亡くなってしまうというデータがあります。また心臓突然死がある弁膜症でもあります。
現在日本では重症の大動脈弁狭窄症に関しては手術が第一選択ですが、カテーテルによる弁置換術(TAVI 「タビ」とよみます)も全国的に治療件数が増えてきており、より低侵襲でうけれる治療として選択肢がふえてきました。内科的な管理(高血圧や心不全・不整脈に対する薬物治療)も並行して行い、重症の場合に関しては、病院での手術やカテーテル治療をまず考えていただく形になります。
大動脈弁閉鎖不全症・・・大動脈弁がうまく閉まらず、逆流が生じている状態です
大動脈弁閉鎖不全症は器質性のものとしては、二尖弁、リウマチ熱、加齢性、感染性心内膜炎があげられます。また弁の根本(基部)が拡大することにより、逆流がおきるとことも確認されていますが、その原因としては加齢、Marfan症候群、大動脈解離などがあります。
重症の場合は手術が基本になりますが、血圧管理が重要になり、内科治療も並行しておこなっていきます。
※近隣の総合大雄会病院、一宮市立市民病院、一宮西病院との連携も密にしています。手術適応になりうる場合や精密検査が必要な場合は総合病院にすぐにご紹介させていただきます。